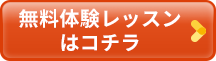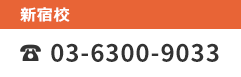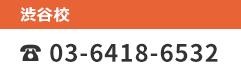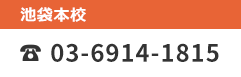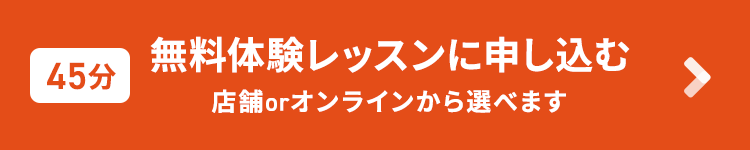ピアノが上手くなる方法5選!今日からできる効果的な練習法を紹介
ピアノ上達方法・テクニック
2025/09/30

ピアノが上手くなるためには、効果的な練習法とコツを抑えることが重要です。
本記事では、ピアノが上手くならない主な理由と、確実に上達するための5つの具体的な練習方法を詳しく解説します。練習の効率化から楽譜の活用方法、実践的なテクニックまで、上達に必要な要素を紹介していきます。
この記事で紹介する方法を実践することで、短い練習時間でも効率的に技術の向上が望めるでしょう。正しい練習方法を身につけ、着実な上達を実感しながら、ピアノ演奏を楽しみましょう。
ピアノが上達しない主な理由
ピアノの練習に時間を費やしているにもかかわらず、思うように上達を実感できないという経験はありませんか。なかなか上達しないと感じる場合は、以下のように練習方法に問題があるかもしれません。
- 部分的な練習をしていない
- 片手での練習がしっかりできていない
- 楽譜に書き込みをしていない
- 上達しない原因を考えていない
ピアノの練習に時間を費やしているにもかかわらず、思うように技術が向上しない原因について詳しく解説します。
部分的な練習をしていない
ピアノがなかなか上達しない原因の1つとして、部分的な練習をしていないことがあります。
曲の最初から最後までを通しで何度も弾く方法は、一見すると堅実な努力のように見えますが、実はあまり効率的ではありません。この方法だと、すでに問題なく演奏できる箇所にも時間を割いてしまい、本当に練習が必要な部分にかけるべき時間が十分に取れないまま進んでしまいます。
このような非効率的な練習は、せっかくの練習時間が十分に実を結ばず、上達が遅れる原因になります。演奏技術を効果的に向上させるには、ただ時間をかけるだけでなく、明確な計画をもって練習に取り組むことが大切です。
片手での練習がしっかりできていない
上達を妨げる原因として、片手での練習がしっかりできていないことも挙げられます。
ピアノの練習において、両手での練習に過度にこだわることは、上達を遅らせる原因となります。片手練習は簡単すぎる練習に感じるかもしれませんが、演奏技術の向上には欠かせない重要な練習です。
両手同時の練習だけを続けると、1本1本の指に意識を向けることができず、細かいコントロールがおろそかになります。そのため、ミスタッチが多くなったり、音量のバランス調整ができなかったり、思い通りに演奏するまでに多くの時間を費やすことになります。
楽譜に書き込みをしていない
同じ箇所で繰り返しミスをしているにもかかわらず、楽譜に何も書き込みをしていないということはありませんか?
演奏の精度を高めるために、つまずきやすい箇所に注意点を記入するようにしましょう。自分だけのリマインダーを楽譜に残すことで、演奏の流れを維持しやすくなります。
特に難しい箇所での指使いや、注意が必要なリズム、強弱の変化など、演奏中に意識すべきポイントを明確に記録することで、練習効率は大幅に向上します。
上達しない原因を考えていない
ピアノが上達しない原因を考えずに練習を続けていても、上達は見込めません。多くの人は、自身の問題点を具体的に見極められず、闇雲に練習を続けてしまいます。
上達を感じられないときは、まず自分の演奏を客観的に分析し、どこに問題があるかを明確にすることが肝心です。自己分析が難しい場合は、演奏を動画に収めて自身の演奏を見直す時間を作りましょう。
【徹底解説】ピアノが上手くなる5つの方法とポイント
ピアノの演奏技術を着実に向上させるためには、効果的な練習が必要不可欠です。効果的な練習方法により、短い時間でも確実に上達できます。
ここでは、ピアノが上手くなるための5つの具体的な方法とそのポイントを解説します。
- 練習パターンを作る
- ピアノを弾く前に準備をする
- 効率的な練習をする
- 楽譜をスムーズに読む
- 自分の演奏を客観的に見直す
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 練習パターンを作る
ピアノの上達のためには、適切な練習ルーティンを組むことが鍵となります。毎日の練習に一定のパターンを取り入れることで練習を習慣化でき、効率的なスキルアップが可能になります。
基本的な練習パターンには、指のウォーミングアップ、基礎練習、課題曲の練習などを組み込むようにしましょう。
自己流で好きなときだけ練習するよりも、無理なく続けられる練習スケジュールを設定し、集中力が高まる環境での練習を心がけると、練習の質も向上します。
1日に最適な練習時間
初心者の方には、1日20分の練習から始めることをおすすめします。上達してきた場合でも、40分を上限としましょう。
人間の集中力には限界があり、40分を超えると学習効率が著しく低下する傾向が見られます。練習の質を維持するためには、1回の練習時間を40分以内に設定するのが効果的です。
より長時間の練習を希望する場合は、40分の練習後に10分程度の休憩時間を設けることをおすすめします。休憩を取ることで集中力が回復し、再び質の高い練習に取り組むことが可能になります。
【あわせて読みたい】「ピアノの上達に必要な練習時間の目安や時間の作り方」
理想的な練習頻度
理想的な練習頻度や時間帯は、自分自身の生活リズムに合わせて決めましょう。
毎日少しずつでも練習を続けるとピアノの上達が早くなりますが、仕事や家事など生活リズムに合わせて週3~4回でも構いません。無理のない範囲で、実現可能な練習頻度を設定し、継続的な練習を心がけることが大切です。
また練習の時間帯は朝や夜など、自分が最も集中しやすい時間を見つけることがポイントです。複数の時間帯で練習してみて、最適な時間を見つけましょう。
【集中力を高める練習場所】
効果的なピアノ練習には、練習環境を整えることが重要です。集中力を維持できる静かな環境を確保することで、練習効率は大幅に向上します。
騒音や視覚的な刺激が多い場所での練習は、注意力が分散し、効果的な練習の妨げとなります。可能な限り、外部からの干渉が少ない専用の練習スペースを確保するのが理想的です。
たとえば、練習室や自宅の個室など、周囲の雑音が遮断された環境を整えることで、楽譜の読み取りや音の確認に集中できます。また、適切な照明や温度管理も、快適な練習環境の要素となります。
2. ピアノを弾く前に準備をする
効果的な練習には、ピアノを弾く前の準備も欠かせません。指のウォーミングアップや正しい姿勢を意識することで、練習の成果が出やすくなります。
また、最初に基礎トレーニングを取り入れ、身体をピアノに慣らすことで、上達が早く感じられるでしょう。
指のウォーミングアップ
効果的な指のウォーミングアップとして、指先のストレッチをご紹介します。演奏前のほんの数分間で演奏の質が向上しますので、ぜひ取り入れてみてください。
【ストレッチのやり方】
- 片手を水平に伸ばし、手のひらを下向きにする
- 肘を直角に曲げる
- もう片手で薬指の先を持ち、やさしく反らせる
- その状態でほかの指を曲げたり伸ばしたりする
- すべての指で同様の動作をおこなう
- 最後に指の間を広げるストレッチを加える
ストレッチをおこなう際は、過度な負荷をかけずに実施することが重要です。強い痛みを感じた場合は、強度を弱めるか中止するようにしましょう。
【あわせて読みたい】「指を早く動かすコツとためになる指先のストレッチ運動」
正しい姿勢とフォーム
長時間練習するには、正しい姿勢が大切です。鍵盤の重みを活かした美しい音色を奏でるため、以下の4つのポイントを意識しましょう。
【基本的な座り方のポイント】
- 着席位置:椅子の前方に腰かける
- 演奏距離:鍵盤とお腹の間は子ども一人分のスペースを確保する
- 高さ調整:肘と鍵盤が水平になるよう椅子の高さを設定する
- 足の位置:両足を床にしっかりとつける
可能な場合は鏡を横に設置し、鍵盤に近づきすぎていないか、肩や肘が不自然に上がっていないかをチェックしてみてください。
ハノンによる基礎トレーニング
ハノンは、60種類の体系的な練習曲で構成され、多くのピアノ教室で採用される定番教材です。ハノンの練習は、指の独立性と基礎的な演奏技術を向上させる効果的なトレーニング方法です。規則的なパターンの反復練習は、指の筋力と柔軟性を向上させることにもつながります。
最初はゆっくりとしたテンポで始め、指の動きを正確に覚えることからスタートすると、基礎がしっかりと身につきます。また、片手ずつ丁寧に練習することで、より正確な指の動きを身につけることが可能です。
3. 効率的な練習をする
ピアノの上達には、ただ弾くのではなく、効率的な練習が求められます。上手く弾けない部分を集中的に練習したり、片手ずつ分けて練習したりするなど、計画的に進めることで目標に早く到達できるでしょう。
ここでは、より効率的に曲を習得するためのポイントをご紹介します。
通し演奏と部分練習
スムーズな演奏を実現するには、練習方法を工夫することが大切です。特に、通し演奏と部分練習を適切に組み合わせることで、効率的な上達が望めます。
通し演奏は曲の全体像を理解し、音楽的な表現を磨くのに効果的です。一方、部分練習は技術的な課題のある箇所を重点的に改善できます。両者をバランスよく取り入れることで、上達につながるでしょう。
たとえば、練習の冒頭で1~2回通し演奏をおこない、課題となる箇所を特定します。その後、問題のある部分を集中的に練習し、最後に再度通し演奏をおこなうことで、改善の成果を確認できます。
右手と左手は別々に練習
片手ずつの練習を徹底することは、正確な演奏技術を身につけるための効果的なアプローチの1つです。一見地味に感じられる片手練習ですが、それぞれの手の動きや音楽的表現を1つずつ確実に習得できる点がメリットです。
両手同時の練習だと、細かな動きや音の強弱、フレージングなど、つい見落としがちな要素も多くなりますが、片手練習ではそれらを細かく確認できます。また、技術的な課題を見つけ出し、改善するためにも片手ずつの練習が役立ちます。
新しい曲に取り組むときには、まず右手と左手を別々に、正確に演奏できるまで練習するのが効果的です。その後、ゆっくりとしたテンポで両手を合わせて練習することで、スムーズな演奏が実現しやすくなります。
スローテンポで練習
正確な演奏技術を身につけるためには、ゆっくりとしたテンポで練習を進めることが重要です。速いテンポで練習すると、誤った奏法が習慣づいてしまったり、不必要な力みが生じやすくなったりします。
スローテンポでの練習では、音の正確さや指の動き、手首の使い方など、演奏に関する細かな部分に集中できます。また、音楽的な表現や強弱のニュアンスも、ゆっくりとしたテンポで丁寧に学べます。こうした細部に注意を向けることで、基礎がしっかりと整うでしょう。
4. 楽譜をスムーズに読む
読譜力を向上させることは、ピアノの上達に不可欠なスキルです。楽譜をスムーズに読めるようになると、新しい曲にも挑戦しやすくなります。
また、音符を効率的に読み取る練習を積むと、より演奏に集中しやすくなります。
楽譜の先読み
読譜は、文章を読むときと非常によく似ています。文章を読む際、1文字ずつではなく単語で把握していくように、楽譜も1音ずつ追うのではなく、音符のまとまりを把握することが重要です。
たとえば、演奏中は常に1~2小節先を意識するようにするのが理想的です。演奏している箇所より数小節先を読み進めることで、スムーズな流れを維持できます。
また、初見演奏の際には、次に来るフレーズやテンポ、強弱の変化を事前に把握することで、余裕を持った演奏が可能になります。
【あわせて読みたい】「譜読みの基礎知識や早く読めるようになるコツを紹介」
ふりがな付き楽譜の活用
ピアノ初心者で、楽譜が読めないことで挫折してしまう方は少なくありません。そのような場合には、ふりがな付きの楽譜を活用することで、より楽しくピアノ学習を進められます。
ふりがな付き楽譜は、音符の上下にドレミがカタカナで表記されており、視覚的に音が把握しやすくなっています。そのため、加線の多い音符や、臨時記号の付いた音符の読み取りも容易です。
ただし、依存しすぎないよう、徐々にふりがなのない楽譜に移行するようにしましょう。
5. 自分の演奏を客観的に見直す
演奏を客観的に見直す習慣をつけることは、技術向上のための大切なステップです。演奏中は気づきにくい癖や問題点も、自身の演奏を外部から観察することで明確に把握できます。
また、周りの人からフィードバックをもらうことも効果的です。
録音・録画で自己チェック
演奏技術の向上には、客観的な自己分析が不可欠です。録音・録画による振り返りは、その最も効果的な方法の1つといえます。
たとえば月に1回程度、練習中の曲を記録することで、演奏の変化や進歩を具体的に確認できます。また、演奏会や発表会の前には、本番を想定した録音・録画をおこなうことで、本番での完成度を高められるでしょう。
演奏の質を高めるには、聴き手への伝わり方を意識することが重要です。自己満足の「つもり演奏」から脱却し、確実な技術向上を目指しましょう。
フィードバックによる改善
ピアノ演奏の上達には、客観的な評価と適切なアドバイスが欠かせません。自己流の練習だけでは気づかない課題が生じる可能性があります。
周囲からフィードバックをもらうことで、客観的な視点を取り入れた練習が可能になります。ときには、他人の意見が新しい発見や改善のきっかけになることもあるでしょう。
フィードバックをもらった後は、問題点を明確に意識し、その改善に焦点を当てて取り組むようにしましょう。継続的なフィードバックと改善の積み重ねにより、確実な技術向上を実現できます。
ピアノの上達が早い人の特徴は?
ピアノ演奏の上達速度には、個人差が見られます。早期に技術を向上させる奏者には、以下のように共通した特徴が存在します。
- 短時間でも毎日練習している
- 楽しんで練習に取り組める
これらの特徴を理解し、自身の練習に取り入れることで、より効果的な上達が期待できるでしょう。
短時間でも毎日練習している
毎日練習を続けることは、着実な上達への近道となります。上達の早い人たちに共通しているのは、練習時間の長さではなく、その継続性です。たとえ短い時間であっても、毎日ピアノに触れる習慣を持つことが大切です。
上達が早い人は、現実的な目標設定から始めます。5~10分程度の短時間でも、毎日ピアノに触れる習慣を重視しています。与えられた課題を1日1回通して練習する、苦手な箇所を集中的に反復するなど、限られた時間でも質の高い練習を心がけています。
まずは、日常生活で短時間の練習を組み込むことから始めましょう。毎日の小さな積み重ねが、確実な技術向上につながっていきます。
楽しんで練習に取り組める
練習に対する前向きな姿勢と楽しむ気持ちが、上達の実現には必要です。単調な練習の繰り返しは、たとえ短時間であっても意欲の低下を招く可能性があります。
上達の早い人は、練習過程そのものに楽しみを見出し、前向きな気持ちで取り組んでいます。練習の楽しみ方は個人によって異なりますが、自分なりの喜びを見つけることで、練習の質は大きく向上するでしょう。
練習を単なる義務としてではなく、音楽を楽しむ機会として捉えることが、着実な上達への近道となります。
ピアノの練習でよくある質問
ピアノの練習を進めると、さまざまな疑問が浮かんでくることも多いでしょう。以下では、ピアノの素質についてや独学での取り組み方など、よくある質問にお答えします。
ピアノに素質は必要?
ピアノが上手になるために素質が必須かというと、必ずしもそうではありません。ピアノにおける素質とは、リズム感や耳のよさなどの要素を指しますが、これらは後天的に鍛えられる部分でもあります。
特にピアノは、集中して取り組むことでスキルを高めることができるため、素質よりも「続ける力」や「工夫する力」が重要です。ピアノの上達には地道な努力が不可欠であり、続けていくことで誰でも上達することが可能です。
ピアノ初心者の大人が上達するまでの期間は?
初級レベルの楽曲をマスターするには、およそ3か月から半年程度の期間が必要とされています。練習時間を十分に確保できる環境があれば、この期間で両手での基本的な演奏が可能になるでしょう。
演奏技術の到達目標や日々の練習時間によって、習得にかかる期間は変動します。仕事や家事で多忙な方の場合、上達までに1年近くかかることもあります。
しかし、継続的な練習に取り組むことで、大人の初心者でも半年以内に両手での演奏技術を身につけることが可能です。最初は簡単な曲から始めて、徐々にレベルを上げていくことで、着実な上達を実感できます。
ピアノを独学で練習するには何から始めればよい?
独学でピアノを習得するには、適切な自己管理が不可欠です。まずは、教材選びや練習のスケジュール立てをおこない、計画的に始めるようにしましょう。
また、独学で練習する場合は、iPadのようなタブレット端末でピアノの練習用アプリを利用するのもおすすめです。大画面で楽譜や指使いを確認できるうえ、リズムやテンポに合わせたガイドも受けられるため、独学でも基礎練習がおこないやすくなります。弾けるようになりたい曲が特にない方も、アプリ内から気になる曲を見つけられるでしょう。
しかし、ピアノを独学で練習していると、壁にぶつかることも少なくありません。そのような場合は、ピアノのプロに習うことも検討してみましょう。プロの講師から指導を受けることで、独学では気づきにくい細かなテクニックや正しいフォームの確認ができ、短期間で効率よく上達できます。
ピアノが上手くなる方法を実践して確実に上達を目指そう
ピアノの上達が進まない多くの原因は、練習方法や取り組み方に隠れています。効率の悪い練習に加え、片手ずつの練習の不足、楽譜を十分に活用していないこと、そして自分の課題を把握しきれていないことが、技術向上の大きな壁となります。
こうした問題を乗り越えるためには、効率的な練習の実践が必要不可欠です。本記事で紹介した練習方法の継続により、着実に上達を実感できるようになります。
しかし、独学での練習に不安を感じる方や、より効果的な練習方法を学びたい方も多いでしょう。そんな方には、Beeピアノ教室の無料体験レッスンがおすすめです。
経験豊富な講師陣が、あなたの現在の演奏レベルを的確に判断し、最適な練習プランをご提案します。また、本記事で紹介した練習方法も、実際のレッスンを通じてより深く理解できます。
まずは気軽に無料体験レッスンを受けて、プロのピアノ講師からアドバイスを受けてみませんか?
「ピアノを確実に上達させたい」方は、Beeミュージックスクールの無料体験レッスンへ


![Beeピアノ教室[Bee piano school]](/piano/assets/img/parts/h-site-logo-piano.png)
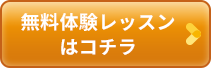
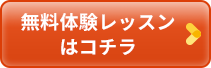
![[フリーダイヤル]0120-015-349(イコーミュージック)携帯電話からも通話可能](/piano/assets/img/parts/h-contact-tel.png)