
「歌が上手い」といわれる人たちには、共通していることがあります。それは、「一般人には真似のできない発声」でも「習得に時間がかかるテクニックを持っていること」でもありません。
歌が上手い人に共通しているのは、「音程の正確さ」と「リズム感」の2つが備わっていることです。
「なんだ!そんなこと?」と思う方もいるかもしれません。しかし、この2つが備わっていないと、どんなに素晴らしいテクニックを持っていても「歌が上手」と思ってもらうことは難しいのです。
本記事では、ボイストレーナー歴15年の僕が、歌が上手くなるための2つのポイントとレッスンにおいて多くの方を上達に導くことのできた「一番効果のある練習方法」、そして習得しておくとかっこよく聞こえる歌唱テクニックを紹介します。
「アーティストのようにかっこよく歌いたい」「人前で自信をもって歌いたい」という方は、ぜひ最後までお読みください。
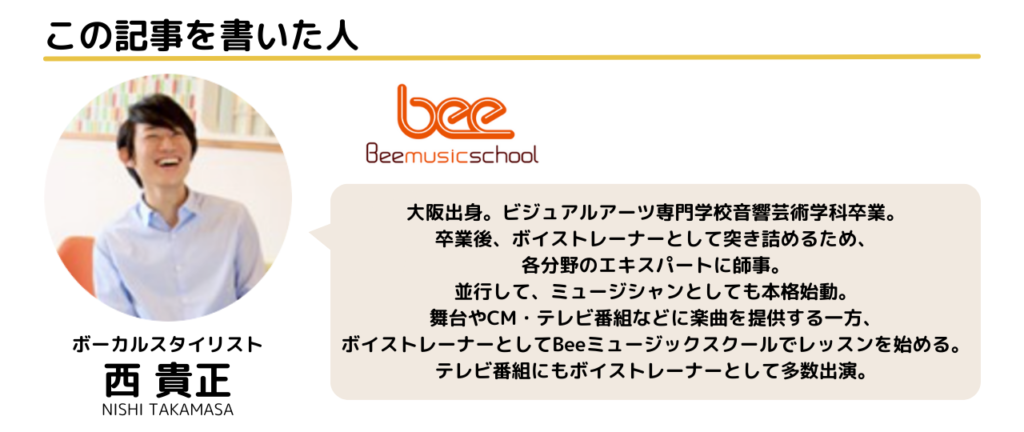
目次
歌が上手いと言われる人には、そうでない人と比べると、以下の2つがしっかりと備わっています。
基本的なことと思う方もいるかもしれませんが、これらを蔑ろにしては、どんなにかっこいいテクニックを身につけたとしても、歌を上手に聴かせることは難しいのです。
本章では、この2つのポイントの重要性をそれぞれ詳しく解説していきます。
歌が上手いといわれる人は、音程が正確であり、一つひとつの音を出すのに迷いがありません。そして、次の音に移るまでに音がブレることもないのです。
わざと元のメロディーから崩しているのに、しっかりと歌えている人を見かけることがありますよね。メロディーを崩してもしっかり歌えるのは、「ドレミファソラシド」のそれぞれの音程が正確であるからです。一方、音程に自信がなく音を探りながら歌ってしまう人がいますが、この場合は次の音に追いつけないため、上手く歌えません。
カラオケの「採点機能」で、メロディーの音の上下が見えるのはご存知だと思います。音を外さずに歌いきることをゴールにしているテレビ番組もよく見かけますよね。これらは、歌う人の音程の正確さ、次の音に移る際の音のブレがないかを見ています。
「私は音痴だから……」と諦めていませんか?練習を繰り返すことで、音程を正確に出すことは可能です。どんなテクニックを駆使するにも、まずは「音程の正確さ」を身につけることで、表現力豊かに歌を聴かせることができるようになるのです。
音の長さを正確に捉えることのできる力を「リズム感」と呼びます。リズム感があるかどうかも、歌を上手く聴かせるために必要な要素です。これも、カラオケの「採点機能」で把握することが可能です。
一つひとつの音の長さは曲によって決められており、それをつなげるとメロディーになります。リズム感がないと、「ビブラート」や「しゃくり」などといった歌唱テクニックを駆使した際に、タイミングを外して次の音に間に合わないといったことが起きてしまいます。
しかし、リズム感が身につくと、どんなにテンポの速い曲でもタイミングを外すことなく、遅れずに歌うことができるのです。
ここまで、歌が上手い人に共通するポイントをお伝えしました。このポイントを効率よく身につけるための練習方法として効果的なのが、「好きな歌の完コピを目指す」ことです。
完コピのメリットは、その歌で使われている音程やリズム、歌唱テクニックのみを集中的に練習するところにあります。その歌に必要がない歌唱テクニックや発声練習を省けるので無駄がなく、効率的な練習方法といえます。
たった1曲でも完コピできると、別の曲を歌う際にもそれまでとはまったく異なる感覚で歌えるので、驚く方も多くいるほどです。
これまで、多くの「歌が上手くなりたい」という方に実践いただき、最も効果が高いと確信した方法です。次の章で練習方法について具体的に解説していきます。
歌が上手くなるための練習方法を、次の4つのステップに分けて解説します。
前の章でも述べたように、練習のポイントとなるのは「完コピを目指す」という点です。ぜひ参考にして、挑戦してみてください。
まずは、完コピの練習に使う歌を選びます。ジャンルは問いません。クラシックでも、童謡・唱歌でもOKです。完コピするうえで重要なのは、好きな歌を選ぶことです。もしくは、憧れのボーカリストの歌なら何でも構いません。
耳馴染みのない歌を選ぶより、普段聴いている歌を選ぶことで、すぐに練習に取りかかれます。また、上手く歌えるようになったときの喜びも大きいはずです。
歌を選ぶ際は、目指したい歌い方をしているボーカリストを1人見つけておくことをおすすめしています。「ボーカリストの見つけ方がわからない」という人は、YouTubeやInstagramなどで探してみましょう。童謡や唱歌もYouTubeなどで探せば、大抵は声楽家やポップスのボーカリストが歌っている音源を見つけられます。
ほかにも歌を選ぶ際に注意したいのが、難易度です。とても難しい歌を選んでしまうと、練習することが多くなるため注意が必要です(ですが、やりがいもあります!)。
歌を選んだら、まずは最初の一小節のみ何度も繰り返し練習しましょう!「そんなの飽きるのでは?」と思われるかもしれません。しかしやってみると、たった一小節だけでも「このボーカリストはこんなことをしていたんだ」「最初の1音目を正しく合わせるのって難しい」と感じることでしょう。
もちろん、最初に狙って練習するのは「音程」と「リズム」です。特に1音目を外さずに歌えることは、歌が上手である条件の1つといっても過言ではありません。
リズムを崩して歌いたいという方もいらっしゃいますが、どんなプロでも最初は正しいメロディー、正しいリズムで練習することがほとんどです。それができて初めて、かっこよくアレンジして歌うことができるのです。
また、余裕があるならそれを歌っているボーカリストの息の混ぜ方、声色、口の開け方、響かせ方、声量、テクニックや癖などを細かく真似していきます。このように細部まで真似することを「完コピ」と呼びます。これが最も効率よく歌が上手くなる方法です。
完コピについて「誰かの真似をするなんて、オリジナリティが出ないのではないか?」「自分のよさをかき消してしまうのではないか?」と言う方がいますが、安心してください。この練習方法を実践した方は、単なる真似で終わることなく、自分らしい歌を見つけられています。
これまで担当したレッスンで最も細かなアドバイスは、「フレーズの最初の一文字だけ抜き出して、正確な音の高さ、そのボーカリストの息の混ぜ方や声量、口の開け方、響かせ方などを完コピする」というものでした。
「そんなに細かく練習しなければならないの!?」「歌の練習が嫌いになりそう」と思われるかもしれませんが、一文字だけの練習でもたくさんの気づきを得られます。「一文字だけでもおもしろい!」と言われる方も多いので安心してください。
練習する範囲をなるべく短く区切ることで、1つのメロディー(フレーズ)に対する意識が変わり、見違えるような歌を歌えるようになります。特に冒頭からお伝えしている「音の正確さ」と「リズム感」は僕の経験上、最初は短いフレーズで練習するほうが圧倒的に上達が早い傾向にありました。
細かく音を捉える意識がつくことで、それまで何となく聴いているだけでは気づけなかったテクニックが見えてくることもあり、ますますその歌やボーカリストへの愛情が深まる方も多くいます。音楽の聴き方が変わり、楽しさが倍増しますよ!
細かい練習がある程度終わったら、自分の歌声を録音して聴いてみましょう。以下の視点をポイントに、自分の歌声を聴いてみてください。
| ポイント | 解説 |
| 音程は正しいか | おすすめは、音源を流しながら合わせて歌ってみることです。オリジナルのメロディーとズレている部分を見つけやすくなります。 |
| リズムは正しいか | 音程のチェック同様、音源を流しながら合わせて歌ってみましょう。ズレているところを顕著に見つけられます。 |
| ズレている部分に共通点はないか | 何曲か試してみると、ズレている箇所に共通点が見つかることがあります。「音程が上がっていくメロディーのときにズレることが多い」「音程が大きく離れているときにリズムがズレている」など。それに気づけば、次に注意しながら歌うことができます。 |
自分ではできているように思えても、客観視して聴き返すと、案外そうでないと気づくことが多々あります。
外国語の練習と同じです。録音して聴いて、できていないところを修正する。この繰り返しが最短距離で上達へ導いてくれます。
歌における基礎は「音程」と「リズム」といわれています。この2つさえ固めておけば、どんな曲を歌ってもかっこよく聴かせることができるようになるのです。
「自分の声を客観的に聴いても、できているのか判断できない…」という方は、勇気を出して誰かに聴いてもらい、感想をもらうのがおすすめです。
ボーカルレッスンの受講を検討してみるのもよいでしょう。ボーカルレッスンでは、ボイストレーナーが現状を細かくフィードバックしてくれたり、できていない部分に対するアドバイスをしてくれたりします。
特に音程を正確に捉えることは、とても難しいものです。毎日正確な音を耳にし、意識しているプロだからこそ、自分だけでは気づきにくい視点で教えてもらえるでしょう。
ここまで、「好きな歌を用いて細かく練習する=完コピの練習方法」についてお話ししました。しかし、以下のような方もいるでしょう。
「音程の正確さを身につけるために、もっと複雑なメロディーで練習したい」
「1曲ずつ完コピするのではなく、どんな曲にも応用できるような練習がしたい」
そんな方には、少し上級者向けの練習方法である「ソルフェージュ」がおすすめです。ソルフェージュとは、楽譜を読む力を学ぶ訓練方法です。ボーカルレッスンにおいても、音程の正確さやリズム感はもちろん、あらゆる歌唱テクニックの習得に役立ちます。
ソルフェージュの教本を見てみると、歌詞のないメロディー集であることが一目でわかります。最初のページはシンプルなメロディーなのですが、ページをめくるごとに複雑な音程やリズムのメロディーとなっていくのです。
クラシックを歌う人のためのものというイメージが強い教本ですが、意外なことにロックやR&Bをマスターしたいボーカリストにも大きく役立ちます。実際、R&Bなどに見られる「フェイク」などに必要な細かな音程の練習に役立つページも存在します。
ソルフェージュの教本を参考に、最初はピアノなどの楽器で音を確認しながら合わせて歌う練習をします。慣れたら伴奏や楽器で弾くガイドメロディーなしに、アカペラで歌います。普段耳にすることのないメロディーを覚えて歌うことで、さらに音程やリズムに対する意識が深まるのです。
1人でおこなうのはなかなか難しいので、ご興味のある方は「ソルフェージュを用いた練習をしたい」とボイストレーナーに尋ねてみるのもよいでしょう。
歌が上手い人に共通するのは、「音程」と「リズム感」のよさであることはお伝えしたとおりです。しかし、歌が上手い人はそれに加えて、効果的に「歌唱テクニック」を取り入れています。
今回はそのなかでも特にメジャーで、習得すると格段にかっこよく聞こえるテクニックを紹介します。
ビブラートを知らない人はいないといえるほど有名なテクニックで、カラオケの採点機能では加点ポイントの対象になります。歌詞の中の1音に「音程を上下させる揺れ」を加えるテクニックで、これができるだけで「上手い!」という印象を決定づけられるので特におすすめです。
多くのボーカリストが多用しているテクニックですが、顕著なのはクラシックのオペラ歌手や、演歌歌手でしょう。このジャンルではビブラートは必須テクニックといえます。実際、オペラや演歌の派手で大きな揺れのビブラートを真似することで習得できたという方もいらっしゃいます。
フォールといわれてもイメージが湧かない人もいるかもしれませんが、カラオケの採点機能の加点ポイントの対象にもなっています。
前の音を引きずるように次の音に移るテクニックで、ただシンプルに音程を正しく取りながら歌うだけではつまらなく聞こえる際に「なんだかオシャレ!」という印象を与えることが可能です。
これも多くの歌手が取り入れていますが、目立って聞こえるのは平井堅さんやJUJUさんで、とてもわかりやすいと思います。
これは意外かもしれませんが、声量のボリューム調整のことです。音楽の授業で「ピアニッシモ」「フォルテ」などの強弱記号を習ったことを覚えている人も多いと思います。まさにそれを声で表現するのです。
歌が上手いと思うボーカリストを思い出してください。声が小さいところと大きなところと差があるはずです。
たった一小節の中でこの差が激しい表現を見つけることもあるでしょう。歌が上手な人は、声量の調整も上手といえます。
次に、家でできる歌の練習方法を2つ紹介します。
これは僕自身も実践している方法ですし、レッスンをご受講くださる方にもお伝えしている内容です。とてもシンプルですが、確実に効果がありますので、ぜひ参考にしてみてください。
まず、自分の歌声を録音して研究する方法です。具体的には、以下の手順でおこなうことをおすすめします。
実際に自分の歌声を聴いてみると、「こんな風に歌っているとは思わなかった」「目指したい歌い方と全然違う」などと感じる部分があるはずです。
憧れのボーカリストの歌い方に近づけられるよう、声量のコントロールや口の開け方、声の響かせ方などのテクニックを真似してみてください。歌が上手くなるための練習方法でもお伝えしたように、歌の完コピを目指すことを推奨していますが、少しの意識の変化だけでもグッと見違えるように変わるはずです。
ちなみに、表現を工夫する作業はプロのボーカリストでも必ずおこないます。こういった作業工程を「ボーカル・ディレクション」といいます。ボーカル・ディレクションを挟むことで、「なんとなく歌った歌」よりどんどん「聴いてもらいたい歌」に変わっていきます。
もちろんこれらの工程は、気持ちよく歌うためだけなら必要ありません。あくまで「歌が上手い」と思ってもらえるための練習であることを覚えておきましょう。
上手く歌いたい歌があれば、とにかく聴き込むことが大切です。プロであっても、1~2回しか聴いていない歌を正確に歌うのは難しいことです。
上手く歌えないのは、「覚えていないだけ」であることがほとんどです。逆にいえば、しっかり聴き込んで練習すれば、大抵の場合は上手く歌えるようになります。
よく、元のメロディーを崩して自由に歌うボーカリストを見かけることがありますよね。そういった方も大抵は、しっかり元のメロディーを聴き込み、歌えるようになってからアレンジを加えています。
僕自身、以下のとおりに聴き込んで覚えています。
こちらもそれぞれ解説します。
メロディーを覚える際には、音程とリズムだけに注力してください。ここでは、声質やボーカリストが使用している歌唱テクニックなどの「表現」は無視します。
よく、1コーラス目と2コーラス目でメロディーが異なっている場合がありますよね。そういった点に注意して覚えます。
メロディーを覚えたら、まずは音源を聴きながら心の中で歌いましょう。声を出してしまうと音源がかき消され、間違って覚えていても気づけないことがあるため注意が必要です。
実際の音源を聴きながら心の中で歌うことで、声を出して歌ったときに音源通りにコピーしやすいという効果があります。心の中での自身の歌唱に集中するのではなく、音源を注意深く聴くことが大切です。
心の中で歌う練習を終えたら、いよいよ声を出しての練習に入ります。どんな声でも構いません。
「そもそも高い声や大きい声が出ないから歌えない」という方がいますが、歌いたい歌を軸に練習することをおすすめしています。その理由は、歌いたい歌を軸に練習するほうが、「高い声の練習」や「声量を増やす練習」を集中的におこなうよりも習得が早いのを、これまでのレッスンを通じて痛感しているからです。
歌いたい歌が軸にあることで、音域や習得したい声を明確化しやすい傾向にあります。そのため、まずは歌いたい歌を見つけ、メロディーを覚えることが何よりも大切なのです。
歌が上手くなるためには、好きな歌を完コピすることが効果的とお伝えしました。しかし、「急にカラオケに行くことになったから今すぐ簡単に実践できる方法が知りたい!」「一瞬で歌が上手くなる方法はある?」という方もいるでしょう。
そこでこの章では、すぐに実践できる歌が上手くなる方法を2つ紹介します。
ほんの少しの工夫で変わるので、ぜひ意識してみてくださいね。また、以下の記事もぜひあわせてご覧ください。
【あわせて読みたい】一瞬で歌が上手くなる方法4選!今すぐ家でできるトレーニングも紹介
運動と同じで、歌う前にもストレッチが重要です。ストレッチせずにいきなり歌い始めると、うまく声が出ないだけでなく、喉を痛めてしまうこともあります。
そもそも、音程の練習もリズムの練習も、喉の筋肉が柔らかくなっていないと効果が薄くなってしまう可能性が高いです。体のストレッチと喉のストレッチをおこない、体と喉をしっかりほぐしておきましょう。
喉のストレッチには、唇を「プルルルル」と震わせる「リップロール」がおすすめです。喉の周りの筋肉をほぐす効果があるので、ぜひ試してみてください。体のストレッチは、ラジオ体操のようなものや、YouTubeなどで紹介されている簡単なヨガなどがおすすめです。
また、喉の筋肉は旋回させる動きより、伸ばすストレッチが効果的です。顎を上に向け、首の筋肉が軽く伸び、痛気持ちいいと感じる程度のストレッチをおこなってください。
練習をせずとも、注意深く自分の声を聴きながら歌うことで、ある程度正しく音程やリズムを取れる可能性もあります。
カラオケなど、大きな音にかき消されて自分の声が聞こえづらいという場合は、片耳を手のひらで塞いでみましょう。自分の声を把握することが容易になります。
また、できる人は声を鼻に響かせる分量を増やすことで、自分の声を聴き取りやすくなるだけでなく、音程を正しく取れるようになるケースもあります。
この記事では、上手く歌うためのポイントと効果の高い練習方法、そして歌唱テクニックについて解説しました。
上手く歌えるようになると、「だんだん自分の声が好きになってきた!」と皆さんおっしゃいます。歌が上達すると自信を持てるので、誰かに自分の歌声を聴いてほしいと思うようになる方も多くいます。
今はインターネットやSNSを使って、顔を出さずとも誰かに自分の歌を聴いてもらえる時代です。ミニコンサートを企画し、ご家族や友人の前で披露するといったことも、とても楽しい思い出になりそうですね。
もちろん、今回お話しした内容は、プロの現場でも大事にしている考え方です。メジャーデビューしている方や、舞台で歌う方にとっても必要不可欠なポイントばかりです。ぜひ本記事を参考に、歌の練習の際に意識して取り入れてみてくださいね。
Beeボーカルスクールでは45分間の無料レッスンを行っております。
まずはお気軽に無料体験レッスンをご利用ください。
\無料体験でグッと上達実感!!/
無料体験レッスン\無料体験でグッと上達実感!!/