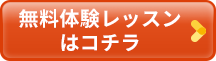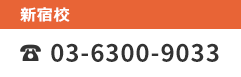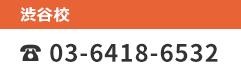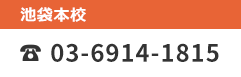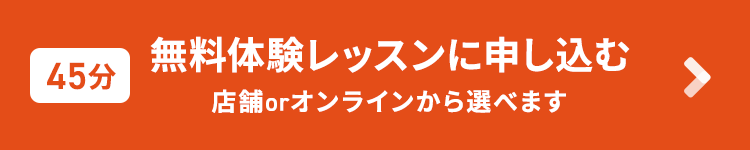プレゼンテーションの話し方が上達するコツとは?出だしの例文も紹介
声
2025/08/31

仕事でプレゼンテーションを任される人のなかには、「プレゼンテーションの話し方が上手くなりたい」と考える人もいるのではないでしょうか。
プレゼンテーションというものは、話し方次第で聞き手への伝わり方が変わります。聞き手が思わず聞きたくなるような話し方を身につけ、プレゼンテーションを成功させましょう。
この記事では、プレゼンテーションの話し方について解説します。上達のコツや事前準備、出だしの例文なども紹介しますので、話し方を知りたい人や何から話し始めたらよいのか悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。
プレゼンテーションは話し方で成功が決まる
プレゼンテーションとは、「情報を相手に伝え、聞く人によい内容だと思わせるコミュニケーション」のことです。
商品やサービス、企画などを一方的に売り込むのではなく、聞き手が話を聞いて、よい内容と思うよう内容や話し方を工夫する必要があります。
資料や話す内容が完璧でも、話し方次第では伝えたいことも上手く伝わりません。聞く人の心に届く話し方はプレゼンテーションの成功に重要なスキルなのです。
プレゼンテーションの話し方が上達する5つのコツ
プレゼンテーションの話し方で悩んだとき、何が自分に足りていないのかを知ることが大切です。改善すべきポイントがわかるので、効率よく練習できます。
プレゼンテーションの話し方が上達するコツは以下の5つです。
- 自分の話し方のクセに気づく
- プレゼンテーションが上手い人の動画を見る
- 抑揚をつけた話し方を練習する
- 制限時間に合わせて話せるよう練習する
- ボイストレーニングをおこなう
項目ごとに詳しく解説します。
1. 自分の話し方のクセに気づく
改善点を見つけるには、自分の話し方のクセに気づくことが大切です。プレゼンテーション中の様子を客観的に振り返り、直したい部分や改善点を見つけてみましょう。
プレゼンテーションの話し方に問題があると感じるなら、練習風景を撮影し、振り返ってみるのがおすすめです。客観的に見ることで、実際に話しているときには気づかなかった改善点が見えてくるでしょう。
撮影動画で話し方を見る際のチェックポイントは以下のとおりです。
- 声の高低や音量は適切か
- 話すスピードは適切か
- 滑舌よく話しているか
- 適度に間を取っているか
- 無駄な言葉の繰り返しはないか
- 視線はどこを向いているか
まず声の大きさです。撮影した映像を見て声が小さく聞こえる場合、息の量が足りていなかったり、上手く響いていなかったりする可能性もあります。口を大きく開けて、ガヤガヤした居酒屋で「すいませーん!」と店員さんを呼ぶような意識をしてみましょう。
声の方向も大切です。原稿を見すぎて下を向いたままだと、声が遠くに届かず、自信がなさそうに見える場合もあります。聞き手のほうを向いて話すと、相手も聞き取りやすくなります。
また、話すスピードや滑舌に問題ないかもチェックしましょう。“間”がない話し方は、相手に考える時間を与えず、急かすような印象を与えるため要注意です。
話を聞いて情報を理解することが得意な人は、約30%といわれています。そのため、資料やスライドなどを見て考える時間が必要ということです。
そのほか、以下の点もチェックしましょう。
- 語尾の締めくくりがいつも同じ言葉になっていないか
- 「頭痛が痛い」などの重複表現になっていないか
- 語尾が伸びるなどのクセがないか
話し方のクセが目立つと、聞き手に不快感を与える可能性もあります。それによって本当に伝えたい内容が薄まってしまっては本末転倒です。
2. プレゼンテーションが上手い人の動画を見る
プレゼンテーションが上手い人の動画を見て、どのような話し方をしているかチェックしてみましょう。話し方の改善につながるヒントが見つかるかもしれません。
参考になる動画は動画サイトでたくさん公開されています。話し方のスタイルもそれぞれ違うでしょう。いろいろな動画を見て、自分が理想とする話し方をしている人を見つけましょう。
「この人の話し方には説得力がある」と思ったら、動画を徹底的に研究してください。声の大きさやテンポ、間の取り方などで気づいた点をメモするとよいでしょう。そのなかから真似できそうなところを取り入れると、話し方が変わってくるはずです。
3. 抑揚をつけた話し方を練習する
プレゼンテーションで棒読みになってしまうのが気になる人は、抑揚をつけて話すよう心がけてみましょう。抑揚とは、声の強弱や高さ、スピードを変えて話すテクニックです。重要な部分を強調したいときや、内容をよりわかりやすく、感情に訴えかけながら相手に届けるための表現方法として使います。
プレゼンテーションは、原稿に沿って伝えたい内容を話していくのが基本です。ただし、原稿や資料を読み上げるだけでは、聞き手の心を動かすプレゼンテーションはできません。聞いてほしい部分が伝わるよう、抑揚をつけて話すことが大切です。
特に目立った抑揚をつけるのは話の重要な部分です。たとえば、商品名や機能性の高さ、実績、数値など、声の調子や大きさが変われば、聞き手も耳を傾けるでしょう。重要な部分に抑揚をつけて話すよう練習してみましょう。
ただし、抑揚のつけ方にも注意点があります。急に声を張った印象になったり、抑揚をつけ過ぎて相手に伝わりにくかったりすることがあります。それでは強調したい部分がどこなのかわからなくなってしまいます。練習風景を動画撮影し、不自然な抑揚がついていないかチェックするとよいでしょう。
抑揚について、詳しくは以下の記事も参考にしてください。
【あわせて読みたい】話し方に抑揚をつける方法や習得するメリットを解説
4. 制限時間に合わせて話せるよう練習する
制限時間を守って話せるよう、時間を意識して話すよう練習しましょう。時間配分の上手さもプレゼンテーションの話し方が上達する要素です。
プレゼンテーションによっては、制限時間が設定されている場合もあるでしょう。時間がオーバーしても足りなくても、タイムスケジュールが決まっている場合などは予定がずれてしまい、迷惑をかける恐れがあります。
普段話し慣れておらず、緊張して時間より早く終わってしまう心配がある人もいるでしょう。そういった人は、練習はもちろんですが、時間が余った際に話す内容を事前に決めておくことも一つの安心材料になります。
聞き手に重要な部分を集中して聞いてもらえるように、考えた構成で制限時間に合わせて話せるよう練習しましょう。
5. ボイストレーニングをおこなう
「滑舌の悪さが気になる」「魅力的な声になりたい」と思うなら、ボイストレーニングに取り組んでみましょう。滑舌が改善されれば、相手が聞き取りやすくなることはもちろん、声色によって聞き手が受ける印象も随分変わるものです。
話し方の悩みに応じて、ボイストレーニングでおこなうトレーニングの方法はさまざまです。声が小さいなら声量を大きくするのに効果的なトレーニングをおこないます。また、滑舌が悪いなら、言葉を明瞭に話せるようになるトレーニングを取り入れるとよいでしょう。
「自分に合ったボイストレーニングがわからない」という人もいると思いますので、独学で難しければボイトレ教室に通う方法もあります。講師による効果的なトレーニングで、プレゼンテーションの話し方を改善しましょう。
新宿・渋谷・池袋・赤羽エリアのBeeボイススクールなら、多彩なコースから話し方の悩みに合った実践的なレッスンが受けられます。プレゼンテーションが上手くなりたいなら「プレゼンコース」、滑舌を改善したいなら「滑舌改善コース」がおすすめです。
Beeボイススクールには無料体験レッスンもあり、実際のレッスンを体感してから受講を決められます。プレゼンテーションの話し方を改善したい人はぜひ試してみてください。
プレゼンテーションで上手く話すための事前準備
プレゼンテーションを成功させるためには、事前準備も重要です。準備のポイントは以下の3つです。
- 聞き手に与えたい印象を考える
- 構成を決める
- 最も伝えたいことをメモ書きする
各項目について詳しく解説します。
1. 聞き手に与えたい印象を考える
プレゼンテーションでは、まず聞き手にどんな印象を与えたいか考えます。与えたい印象により話し方を変えたほうが、プレゼン内容が効果的に伝わるからです。
プレゼンテーションの話し方は、内容や聞き手の属性により変えるとよいでしょう。聞き手に信頼してほしいときは、責任感や誠実さをアピールする話し方が合います。親しみを持ってほしいときは、親近感の持てる温かみのある話し方にしてみてください。
与えたい印象がはっきりすれば、服装やヘアスタイルも決まります。身だしなみと話し方をリンクさせ、聞き手にメッセージが伝わりやすいように工夫しましょう。
2. 構成を決める
次にプレゼンテーションの構成を決めます。話しやすいよう、内容が簡潔に伝わるような構成を考えるとよいでしょう。
構成を考える際「型」に当てはめると整理しやすくなります。プレゼンテーションの構成に使える型は以下のとおりです。
- 三段構成(序論・本論・結論)
- SDS法(概要・詳細・要点)
- PREP法(結論・理由・具体例・ポイント)
- DESC法(描写・表現・提案・選択)
三段構成は基本の型で、レポートや論文でもよく使われます。SDS法は概要を細かく伝えたいときに便利です。
PREP法は最初に結論を伝え、聞き手を説得したいときに有効です。DESC法は聞き手との合意点を探る手法です。相手の反応に合わせ、選択肢を変えたいときに使います。
性別的な意味ではなく思考癖として、男性性の強さは結論を先に求め、女性性の強さは共感を求めやすいという傾向もあるので、相手によって合わせる方法もあります。
3. 最も伝えたいことをメモ書きする
最後に、一番伝えたいことを意識しながら話せるよう、重要部分や語句をメモ書きしましょう。緊張していても、要点を押さえて話しやすくなります。
プレゼンテーションで緊張しやすい人は、壇上で頭が真っ白になってしまう場合もあるでしょう。原稿のどこを読んでいたのかわからなくなってしまうかもしれません。そのようなときも、保険として重要ポイントを書いたメモを持っていれば安心です。
メモには、構成ごとの伝えたい内容を箇条書きで書きます。最も伝えたいことは、聞き手の悩みや課題解決に役立つ内容から選びます。「性能が〇%アップ」「シェアNo.1」など、数値を入れると聞き手もイメージしやすいでしょう。
プレゼンテーションの出だしの話し方と例文
「プレゼンテーションの出だしで何を話したらいい?」と悩む人もいるのではないでしょうか。聞き手が内容に興味を持てるよう、出だしを工夫しましょう。
プレゼンテーションの出だしのポイントは以下の5つです。
- 聞き手が共感できる話題を入れる
- 疑問形で聞き手に問いかける
- 具体的な数字を入れる
- 自分の体験談を話す
- 格言や名言を取り入れる
各項目について詳しく解説します。
1. 聞き手が共感できる話題を入れる
聞き手が内容に興味を持てるよう、出だしには聞き手が共感しやすい話題を入れるとよいでしょう。話し手が似たような経験や感情を持っていると、自分のことに当てはめて考えやすいためです。
聞き手の共感を得るには、聞き手の持つ悩みや課題を想像することが大切です。例文を紹介します。
- 私は仕事中、〇〇が上手くいかず悩んでいました。
- 皆さんは〇〇で悩んだ経験はありませんか。実は私もそうでした。
このように、聞き手に共感してもらえるような話題を考えてみましょう。
2. 疑問形で聞き手に問いかける
出だしで聞き手を巻き込んでしまう方法もあります。聞き手を参加させることで当事者意識を持ってもらうための効果的な方法です。
疑問形で聞く方法には、クイズやアンケートがあります。プレゼンテーションにつながる内容のクイズを出し、賛成と反対で挙手するよう指示を出します。選択肢をいくつか出し、それぞれ挙手してもらうのもよいでしょう。
出だしに問いかけることで、内容に興味を持つ人を増やせる可能性があります。疑問を解決するため、この続きを聞きたいと思うきっかけになるのです。
3. 具体的な数字を入れる
話す内容に説得力を持たせたいなら、出だしの内容に具体的な数字を入れてみましょう。データを使うと説得力が増し、聞き手の興味を引き付けやすいためです。
たとえば、実績数をアピールしたい場合です。「多くのプロジェクトに携わりました」では、どのくらいの件数なのかわかりません。「1年間で〇〇件のプロジェクトに携わりました」のほうがイメージしやすくなります。数字を上手く取り入れると、信頼度が増すのです。
また、聞き手に危機感を持たせるために数値を使う方法もあります。たとえば「今のままでは10年後に生き残る会社は〇割です」などです。現状を改善したいと考え、本題に興味を持つきっかけになるでしょう。
4. 自分の体験談を話す
プレゼンテーションの内容につながる体験談があれば、ストーリー仕立てで話すのもおすすめです。それにより、聞く人の共感や関心を得やすくなります。
短い物語を話し、聞き手に興味を持たせる手法を「ストーリーテリング」といいます。本題と関係し、聞き手の疑問や課題に寄り添った内容であればベストです。
ただし、凝った物語やウケを狙った物語を考える必要はありません。本当に伝えたいのは出だしではなく本題の部分です。あくまでも導入部分として、本題に関わるエピソードや体験談があれば充分使える方法です。
5. 格言や名言を取り入れる
聞き手に印象を残したいなら、出だしに著名人の言葉や格言を取り入れてみましょう。最初にインパクトを与えることで、聞き手の興味をひきつける効果があります。
格言や名言は、短い言葉で心に響く魅力があります。古くからいわれている言葉や、著名人の言葉なので権威性があり、聞き手を納得させやすいのです。
日本人の格言を使うのもよいですし、外国の格言を英語で話してもよいでしょう。聞き手がもっと話を聞きたくなるよう、格言や名言を効果的に使いましょう。
プレゼンテーションの話し方の極意9選
プレゼンテーションの話し方で、ぜひ気をつけてほしい点は以下の9つです。
- 伝えたい内容を強調して話す
- 伝わりやすい言葉を使う
- 聞こえやすい声の大きさでゆっくり話す
- 「間」を上手く使う
- ドッグワードに気をつける
- 内容に合わせてジェスチャーを入れる
- 語尾のクセに気をつける
- 聞き手の顔を見るよう心がける
- 腹式呼吸を意識して話す
各項目について詳しく解説します。
1. 伝えたい内容を強調して話す
まずは、一番伝えたい内容を意識し、聞き手に伝わりやすい話し方を心がけましょう。ほかよりも強調したり、わざとゆっくり話したりすることで、どこが重要なのか伝わりやすくなります。
強調したい部分を印象づけるためには、声の強弱を利用するのがわかりやすいでしょう。大きな声で話すと、「ここは大事な部分」だと聞き手に伝わります。また、小さな声で話すとよく聞こうと聞き手が耳を傾けるので、大事な部分をあえて小さく話すのも効果的です。
大事な部分を繰り返して強調する方法もあります。内容や聞き手に合った方法で、話し方を工夫してみましょう。
2. 伝わりやすい言葉を使う
プレゼンテーションの場では、難しい言葉ではなく、伝わりやすい言葉を使いましょう。聞き手に専門知識がなくても理解できるよう、わかりやすい言葉選びが基本です。
自分が当たり前に使うビジネス用語でも、聞き手には馴染みがない可能性があります。たとえば「ローンチ」のようなビジネス用語を聞いて、理解できない参加者がいるかもしれません。「発表」や「公開」などに言い換えたほうが理解しやすいでしょう。
どうしても専門用語を使う際は、簡単に解説を添えると親切です。聞き手に伝わりやすいよう、言葉を工夫するとよいでしょう。
3. 聞こえやすい声の大きさでゆっくり話す
本番では、会場の広さに合わせ、聞こえやすい声量でゆっくり話しましょう。意識的にゆっくり話したり声を響かせたりすると、言葉がはっきり聞こえ、聞き手に内容が伝わりやすくなります。
声の大きさだけでなく、話すスピードも伝わりやすさのためには大切です。早口だと言葉がつながって聞こえるため、話の内容をくみ取りづらくなります。
話すスピードとして、内容が伝わりやすく聞き取りやすいとされるのは、1分間に300文字が目安といわれています。どのくらいのスピードで読んだらよいか知るため、300文字の原稿で練習するとよいでしょう。原稿の文字数を数えてくれる「文字数カウント」をネット検索して使用すると便利です。
4.「間」を上手く使う
プレゼンテーションの話し方では、「間」を効果的に使うのがおすすめです。沈黙の時間をつくることで、伝えたい内容を強調できます。
沈黙が怖くてずっと話し続けてしまう人がいますが、効果的な間の取り方で、聞き手に内容をよく聞いてもらえる効果があります。原稿内容を考えるときに間を入れる部分を考え、沈黙を効果的に使いましょう。
間を取るのは、最も伝えたい内容の前後が効果的です。沈黙で聞き手をひきつけ、重要なワードを印象に残してもらうのです。
質問のあとの間も重要です。プレゼンテーションの視聴者ではなく、参加者になってもらうため、聞き手に考える時間を与えたほうがよいでしょう。
5. ドッグワードに気をつける
ドッグワードとは、「えー」「あのー」といった無意識で出る、内容の本筋から外れる言葉のことです。ドッグワードが多いと、思考や方向性に迷いがあるような印象を与えてしまいます。
無意識に出る言葉なので、自覚せず使ってしまう場合もあるかもしれません。実際のプレゼンテーションや練習風景の動画を撮影して、ドッグワードを言っていないかチェックしておきましょう。
特に、予期せぬ質問が来たときなどは、ドッグワードを言いそうになるときもあるでしょう。その場合は、一旦言葉を飲み込み、質問に対する答えをまとめます。話すことが決まるまでは沈黙を上手く使うことで、本筋から逸れるリスクを回避できます。
6. 内容に合わせてジェスチャーを入れる
話すときは、棒立ちのまま話すのではなく、内容に合わせてジェスチャーを取り入れるのがおすすめです。動きを加えると聞き手の注目を集めやすくなります。
オーバーアクションの必要はありませんが、ジェスチャーが多いと、それだけで自信があるように見えます。
スライドの見てほしい部分に手を向けたり、指し示したり、挙手した人をあてるとき手を出したりする程度でも心象よく見えます。
7. 語尾のクセに気をつける
語尾を伸ばす、語尾の声が小さくなるなど、話し方のクセに気をつけましょう。重要なことを伝える場のプレゼンテーションでは、悪い印象を与えかねません。語尾を伸ばす話し方は幼さを感じるため、「本当にこの人に任せて大丈夫か」と頼りない印象になりがちです。
息が続かず語尾の声が小さくなると、何を伝えたいのか曖昧になりますし、自信もなさそうに見えます。逆に語尾を強く言い切り過ぎると、きつい印象を与えてしまうこともあります。
また、「思います」は使わないようにしましょう。会社の代表として話す場所では、自分の考えで曖昧に聞こえるような回答は避けたほうがよいでしょう。わからないことは「後日回答します」と伝えたほうが誠実です。
8. 聞き手の顔を見るよう心がける
話している最中は、聞き手の顔を見るよう心がけましょう。原稿やスライドばかり見ていては、聞き手の反応がわからないためです。
プレゼンテーションもコミュニケーションの一部です。相手を無視した話し方では、聞き手が置き去りになってしまいます。原稿ばかり見ず、聞き手のほうを見て話しましょう。
どの聞き手を見るかは、目的に合わせて変えると効果的です。全体に聞いてほしい場合は、会場全体をブロックに分けて目を配るとよいでしょう。聞いてほしい相手が絞られる場合は、その相手に絞って目線を送るのも効果的です。
9. 腹式呼吸を意識して話す
話す際は、大きな声ではっきり話せるように腹式呼吸を意識しましょう。語尾まで鮮明に伝わりやすくなります。さらに、早口になりがちな人の呼吸を整えることにもなるので、ペースが速くなるのを抑え、緊張をほぐす効果もあります。
緊張すると肩で息をするため、呼吸が浅くなりがちです。そうなると、語尾を話すまでの息がもたなくなります。日本語は最後のほうに動詞や結論が来る言語なので、語尾まで明瞭に話さないと内容が伝わりません。
腹式呼吸を意識すると、緊張が解けて話の最後まで息がもちやすくなります。また、緊張していると喉にも力が入りやすいので、話し始める前に吐くことを意識して体を大きくストレッチしながら数回深呼吸をするのもおすすめです。緊張しやすい人は特に、練習のときから腹式呼吸を意識してみましょう。
プレゼンテーションの話し方練習はボイトレ教室がおすすめ!
プレゼンテーションの話し方に悩んでいる人は、自分の話し方を振り返ってみましょう。声の大きさや抑揚の付け方、話し方のクセなど課題が見えてくるかもしれません。
練習しても「この話し方でいいのか」と不安になる場合もあるでしょう。独学で難しい人は、話し方教室に通ってみるのもおすすめです。プロの目線で客観的に判断し、改善に向けたレッスンを提案してもらえます。
新宿・渋谷・池袋・赤羽のBeeボイストレーニングスクールなら、滑舌や呼吸法、構成など、話し方の悩みに対し充実したサポートが受けられます。マンツーマンでお悩みに応じた効果的な指導が受けられるため、プレゼンテーションの上達が実感できます。
実際のレッスン内容を確かめられる無料体験レッスンもあります。
プレゼンテーションの話し方を練習したいなら、Beeボイストレーニングスクールの無料体験レッスンへ


![Beeボイストレーニングスクール[Bee voice school]](/voice/assets/img/parts/h-site-logo-voice.png)
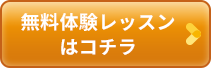
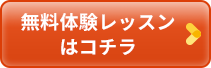
![[フリーダイヤル]0120-015-349(イコーミュージック)携帯電話からも通話可能](/voice/assets/img/parts/h-contact-tel.png)