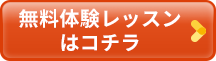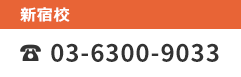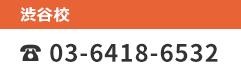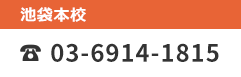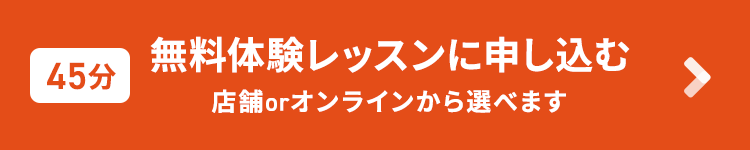プレゼンテーションが上手い人の特徴は?資料作りのコツ・練習方法も紹介
声
2025/09/24

社会人になると、営業先や社内でプレゼンを求められる機会があります。プレゼンを成功させるためには、ポイントを押さえて練習を重ねることが大切です。
本記事では、プレゼンテーションが上手い人の特徴を詳しく解説します。また、プレゼンには欠かせない資料作りのコツや練習方法も紹介します。
プレゼンを成功させたい人や苦手意識のある人は、ぜひ最後までお読みください。
よいプレゼンテーションとは?
聞き手が最後まで興味を持って話を聞いてくれれば、よいプレゼンといえるでしょう。プレゼンテーションの目的は、商品やサービスを紹介し、次の行動につなげることです。
たとえば、紹介した商品を購入してもらったり、サービスを契約したりすることなどがあります。
最後まで話を聞いてもらえるよいプレゼンにするためには、伝えたいことを明確にすることが大切です。話し方や資料の作り方にもポイントがあるため、次の項目から詳しく解説します。
プレゼンテーションが上手い人の話し方・特徴
プレゼンテーションが上手い人には共通点があります。ここでは、話し方・特徴を6つ紹介します。
- 資料を読み上げない
- リズムよく話す
- 聞きやすい声量・速度で話す
- 事例・エピソードを交えて話す
- 結論から話す
- 聞き手に問いかける
プレゼンテーションに自信がない人は、ぜひ参考にしてください。
資料を読み上げない
プレゼンテーションが上手い人はなるべく資料を見ずに、聞き手の様子を見ながら自分の言葉で伝えます。一方で、資料を読み上げるだけのプレゼンは、聞き手に退屈さを感じさせるでしょう。
プレゼンでは、冒頭の挨拶や自己紹介などで聞き手の興味や関心を引くことが重要といわれています。プレゼンの内容すべてを資料なしで話すのが難しい人は、冒頭だけでも顔を上げて聞き手の表情を見ながら話すのがおすすめです。
リズムよく話す
プレゼンでは、聞き手が集中して話を聞けるようにリズム感を大切にしましょう。「あのー」「えーっと」などの言葉が多くなると、リズムが途切れて歯切れの悪い印象を与えます。
テンポよく話を進めるためには、事前準備が大切です。自分のプレゼンを録画して客観的に聞くと、どの部分を改善したらよいかわかりやすいでしょう。
聞きやすい声量・速度で話す
プレゼンする際は、聞き取りやすい声量・速度で話すことが大切です。後ろの席に座っている人にまで届く声で話しましょう。人は感情的になると声が大きく、早口になることが多いといわれています。逆に自信がない場合は、声が小さくなる傾向にあります。
本番前に何度も練習しておくことで自信を持って話せるようになるでしょう。重要な情報をきちんと相手に伝えるためにも聞き取りやすさは大切な要素です。
事例・エピソードを交えて話す
プレゼンで相手に興味を持って話を聞いてもらうためには、事例・エピソードを交えて話すとよいでしょう。具体的な企業・有名人の事例や体験談などを盛り込むと、自分だからこそできるプレゼンになります。聞き手の印象に残りやすい点もメリットです。
ただし、事例やエピソードなどを急に思いつくのは難しいでしょう。そのため、プレゼンで使えそうな体験談、事例は普段からストックすることが大切です。スマートフォンのメモに保存するなどして、活用できる状態にしておきましょう。
結論から話す
プレゼンテーションが上手い人は、結論から話します。結論が後回しになると、何を伝えたいのかわからないプレゼンになるため注意しましょう。
そこで、自分の考えを的確に伝えたいときにおすすめのフレームワークであるPREP法を紹介します。
- P:Probrem(結論)
- R:Reason(理由)
- E:Exprerience(具体例)
- P:Problem(結論)
フレームワークに当てはめると、何を伝えたいのかが明確なプレゼンに仕上がるので、ぜひ試してみてください。
聞き手に問いかける
一方的に話すプレゼンでは、聞き手が集中して聞き続けることは難しいでしょう。集中して話を聞いてもらうためには、プレゼンの途中で聞き手に質問を投げかけることがおすすめです。
「質問はありますか?」「感想はありますか?」などの質問をすると、聞き手の理解度を把握できるメリットもあります。聞き手も的外れな回答をしないように集中して耳を傾けるようになるでしょう。
【準備編】プレゼンの資料作りのコツ
上手いプレゼンをするためには資料作りが大切です。いくら話すのが上手でも、資料がわかりにくいと聞き手に伝わりにくくなります。
ここでは、プレゼンの資料作りのコツを3つ解説します。
- 1スライド・1メッセージにする
- 表・図解を入れる
- 客観的なデータを提示する
それぞれ詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
1スライド・1メッセージにする
1つのスライドに伝えたい内容を複数入れると、聞き手はどの話をしているのかわからず混乱します。たとえば、3つのコツであれば1枚目のスライドで1つ目のコツ、2枚目のスライドで2つ目のコツというように分けましょう。
また、スライドに文字を詰めすぎると、読むことで精一杯になり、話を聞いてもらえない可能性があります。1スライドに70文字以下を目安にしてスライドを作るのがおすすめです。
表・図解を入れる
表や図解を挿入すると、プレゼンの内容がより具体的に伝わりやすくなります。グラフやイラストを入れると、テキストを読まなくても内容が理解できる点がメリットです。さらに、ターゲット層に合ったデザインにすると、聞き手の興味を引けるでしょう。
資料を作成する際は、「この説明をわかりやすいグラフ・表にするにはどうしたらいい?」と常に頭に入れておくことが大切です。
客観的なデータを提示する
プレゼンの資料には、意見の根拠となる客観的なデータを提示することがおすすめです。客観的なデータがあると説得力が増し、聞き手に理解してもらいやすくなるでしょう。
データを使用する際は、必要な部分を抜粋して数値をわかりやすく表示します。単にデータをコピーして貼り付けるだけでは、何を伝えたいのかわからなくなるため注意しましょう。
プレゼン・話し方が上手い有名人3選
プレゼンが上手い人はどのように話しているのか気になる人もいるでしょう。ここでは、プレゼン・話し方が上手い有名人を3名紹介します。
動画を見てよいと思ったポイントは、自分のプレゼンでも取り入れるのがおすすめです。
1. 平井一夫
ソニー株式会社の代表取締役の平井一夫さんは、資料を見ずに堂々と話す姿が特徴です。常に聞き手を見てプレゼンをおこなっています。声のトーンは明るく、口の中も開いているため、明瞭に言葉を聞き取れます。
人前に立つとオドオドしてしまう、どこを見て話せばいいのかわからない人はぜひ参考にしてください。
2. 孫正義
2人目は、ソフトバンク株式会社の代表取締役社長の孫正義さんです。プレゼンする際は資料を見ずに自分の言葉で伝えています。聞き手が聞き取りやすいゆっくりとしたスピードで話している点も特徴です。
また、話の要点を伝え、語尾を言い切りの形にすることで力強さや説得力が感じられます。プレゼンに自信がない人は、よいと感じる点を参考にして取り入れてください。
出典:生成AI「速さから深さに」 ソフトバンクGの孫氏が講演
3. 長岡秀貴
NPO法人侍学園スクオーラ・今人理事長の長岡秀喜さんは、プレゼンで相手の興味を引く点に優れています。プレゼンは最初の印象が重要です。冒頭で興味を持てないと感じると、その後の話を聞いてもらえない可能性が高いでしょう。
長岡さんはプレゼンの冒頭で聞き手の笑いを誘い、聞き手との距離を縮める工夫をしています。『時間という財産』というテーマで内容自体も学びが多いため、プレゼンの仕方がわからない人におすすめです。
出典:時間という財産: Hidetaka Nagaoka at TEDxSaku
プレゼンを成功させるための練習方法
営業先や社内での大切なプレゼンを成功させたいと思っている人もいるのではないでしょうか。プレゼンは、いかに事前準備をきちんとできるかがポイントです。
ここでは、プレゼンを成功させるために必要な練習方法を紹介します。
- 台本を作成する
- 練習を撮影・録音してチェックする
- 第三者からフィードバックをもらう
1つずつ見ていきましょう。
台本を作成する
まずは、プレゼンの台本を作成しましょう。どのような流れで話をするのか、体験談・エピソードを盛り込む場所などをメモしておくと、リズム感のあるプレゼンに仕上がります。
また、本番のシチュエーションを複数想定して台本を用意しておくと、失敗を最小限にできます。たとえば、静けさに包まれた雰囲気と和気あいあいとした雰囲気では、話すトーンや表情も少し異なります。
どのような場面でも対応できるように準備しておくと、自信を持って本番に挑めるでしょう。
練習を撮影・録音してチェックする
プレゼンをしていると、自分を客観的に見るのは困難です。そこで、自分のプレゼンを撮影・録音して、表情や話し方、声量などに不自然な点がないかチェックするのがおすすめです。
伝わりにくい箇所や不自然な箇所を修正すると、クオリティの高いプレゼンができます。ほかの人に見てもらう機会がない場合は、録音と修正を繰り返して練習しましょう。
第三者からフィードバックをもらう
会社の同僚や上司、知人などにプレゼンを見てもらい、フィードバックをもらうのも1つの方法です。第三者に見てもらうことで、自分では意識できていなかった点に気づけるでしょう。
プレゼンを見てもらう際は、事前に目的やテーマを伝えておくのがおすすめです。ネガティブなフィードバックをもらったとしても、本番までに改善すればよいので、過度に落ち込む必要はありません。本番でよいプレゼンができるように何度も練習を繰り返しましょう。
プレゼンテーションが上手い人に関するよくある質問
最後に、プレゼンテーションが上手い人に関するよくある質問に回答します。
- プレゼンが上手い人と下手な人がいるのはなぜ?
- プレゼンの構成のコツはある?
- 話し方以外で気をつけることはある?
プレゼンの注意点やコツを知りたい人は参考にしてください。
プレゼンが上手い人と下手な人がいるのはなぜ?
プレゼンが上手い人は一方的に話すのではなく、聞き手の理解度や反応に合わせて状況判断ができます。また、はじめに結論や聞き手にとってのメリットを伝えて、注意を引く工夫をしている点が特徴です。
一方、プレゼンが下手な人は資料を読むことに必死になり、聞き手のことまで意識できていないことが多くあります。上手いプレゼンをするためには、「自分が聞き手であればどう思うか?」を常に考えることが大切です。
プレゼンの構成のコツはある?
プレゼンでは、何をどの順番で話すのかといった構成が重要です。構成をゼロから考えるのは大変な作業のため、型に当てはめるとスムーズに話せるでしょう。
先ほど説明したPREP法以外にもおすすめの型があるので紹介します。
| 型 | 概要 | 流れ |
| SDS法 | 要点を繰り返して相手の記憶に残す方法。プレゼンや短いスピーチに有効。 | ・Summary(要約) ・ Detail(詳細) ・ Summary(要約) |
| DESC法 | 相手とのコミュニケーションや問題解決に役立つ方法。特に話し合いや交渉に有効。 | ・Describe(現状) ・ Express(問題点) ・ Suggest(提案) ・ Consequence(結果) |
プレゼンの内容や自分が話しやすい型を用いて、プレゼンの構成を作成してみましょう。
話し方以外で気をつけることはある?
プレゼンでは、話し方以外にも気をつけるとよい点がいくつかあります。具体的な項目を以下にまとめました。
- 姿勢:背筋を伸ばして胸を張る
- ボディランゲージ:身振り手振りを適度にする
- 表情:無表情にならないようにする
- アイコンタクト:聞き手と視線をあわせて話す
姿勢や表情などは今からすぐに実践できるため、ぜひ練習や本番で取り入れてみてください。
プレゼンを成功させるならBeeボイストレーニングスクールがおすすめ!
本記事では、プレゼンテーションが上手い人の話し方・特徴について解説しました。プレゼンでは結論から話し、事例やエピソードなどを交えると聞き手に興味を持ってもらいやすくなります。
また、話し方以外にも資料作りのコツや練習方法について紹介しました。プレゼンを上達させるためには何度も練習を繰り返すことが大切です。練習は自分で進めてもよいですが、必ず成功させたいプレゼンがある人や苦手意識がある人は、プロの力を借りることも検討しましょう。
効率よくプレゼンを上達させたい人は、Beeボイストレーニングスクールがおすすめです。発声・滑舌練習から原稿読み、フリートークまで幅広くレッスンを受けられます。45分の無料体験レッスンも実施しているので、気になる人はぜひ活用してください。
「プレゼンテーションが上手くなりたい」方は、Beeボイストレーニングスクールの無料体験レッスンへ


![Beeボイストレーニングスクール[Bee voice school]](/voice/assets/img/parts/h-site-logo-voice.png)
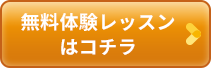
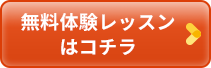
![[フリーダイヤル]0120-015-349(イコーミュージック)携帯電話からも通話可能](/voice/assets/img/parts/h-contact-tel.png)