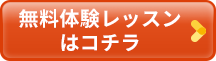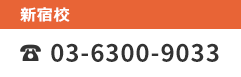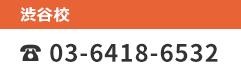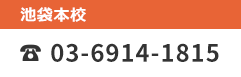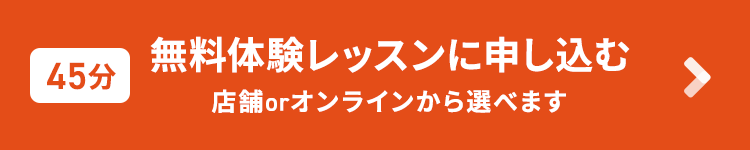【徹底解説】声がこもる人の特徴と原因!5つの改善方法も紹介
声
2025/08/31

声がこもっていると、言葉が聞き取りにくくなるため、他人から「よく聞こえない」「何を言っているかわかりづらい」と指摘を受けることもあるでしょう。
特に子どもの頃から声がこもっている場合には、「遺伝だから仕方ない……」と諦めてしまう方もいるかもしれません。しかし、こもり声は原因を突き止めて正しい方法で対処すれば、改善することが可能です。
そこで今回は、声がこもる人の特徴と原因、適切な改善方法について解説します。こもり声にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
声がこもる人の特徴は?
自分の声は、空気を伝わって耳に届く気導音のほか、骨を介した骨導音も伝わってくるので、かなりクリアに聞こえます。そのため、自分の声がこもっていることになかなか気付かないケースも多いのですが、声がこもる人には以下のような共通点があります。
- 他人から聞き返されることが多い
- 話しかけても気づいてもらえない
- やる気がない・暗いというイメージを持たれやすい
まずは声がこもる人の特徴を知り、自分の声がこもっているかどうかチェックしてみましょう。
他人から聞き返されることが多い
「もう一回言って?」「今何て言ったの?」など、日常会話のなかで何度も聞き返される場合は、声がこもっている可能性が高いといえます。
相手が同じ人なら、聞く側に問題がある可能性もあります。しかし、誰と話しても聞き返されるという方は、こもり声を疑いましょう。
話しかけても気づいてもらえない
声がこもっていると、話しかけても気づいてもらえないことが多くあるでしょう。
特に街中や混雑したお店の中など、騒がしい場所では気づいてもらえない確率が上がります。
やる気がない・暗いというイメージを持たれやすい
「やる気のある人・明るい人=ハキハキ話す」というイメージが定着しているせいか、声がこもっている人は実際の性格や気分とは関係なく、「やる気がなさそう」「雰囲気が暗い」と思われがちです。
友人関係なら、付き合いを重ねていくうちに誤解は解けますが、たとえば就活の面接やオーディションなど一回きりの大事な場面では、致命的な欠点になってしまうおそれがあります。
声がこもる4つの原因

声がこもってしまう理由は1つだけでなく、以下のように複数の原因が考えられます。
- 声が共鳴していない
- 口の開け方が小さい
- 滑舌が悪い
- 姿勢が悪い
ここからは声がこもる主な原因を紹介しますので、自分はどのタイプに当てはまるのかチェックしてみましょう。
1. 声が共鳴していない
人の声は主に、喉(咽頭共鳴腔)と口(口腔共鳴腔)と鼻(鼻腔共鳴腔)に共鳴したものです。
特に鼻は声の抜けがよくなる大切な響きをつくります。鼻に響かせる分量を増やすことができれば、それだけでも劇的に改善させられるほどです。
2. 口の開け方が小さい
声の出口である口の開け方が小さいと、明瞭さに欠けた印象の声となります。
人前で話す場面など、緊張しているときにも起こりがちです。傍目からもブツブツと呟いているように見えるので、「暗い」「陰気」といったイメージを持たれやすいでしょう。
3. 滑舌が悪い
口や舌の動きが鈍いと、発声や発音にも大きな影響をもたらします。
特に舌の動きが悪いと、いわゆる「舌足らず」な発音になってしまい、コミュニケーションの弊害になることがあります。
4. 姿勢が悪い
猫背になっていたり、逆に背筋が反り返っていたりすると、気道が確保されず、十分な量の息を吐くことができなくなります。
また、姿勢が悪い人の多くは腹筋も弱いので、気の抜けたような声になりがちです。
こもり声の治し方は?おすすめの改善方法5選

こもり声は、適切なトレーニングや練習をおこなえば、徐々に改善させることが可能です。ここでは、こもり声を改善するための方法を5つご紹介します。
- 共鳴腔をコントロールできるようにする
- 舌の動きをよくするトレーニングをおこなう
- 腹式呼吸を意識する
- 喉の筋トレをおこなう
- ゆっくりと抑揚をつけて話す
すぐに実践できるものばかりなので、ぜひ試してみてくださいね。
1. 共鳴腔をコントロールできるようにする
共鳴腔を意識して声の響きをコントロールしてみましょう。声は特に鼻に響かせる分量を増やすことで抜け感が増し、人混みの中でも通る声がつくられます。
効果的なトレーニングとして「ハミング」が挙げられます。ハミングはわざと鼻に集中させた声を発声するものですが、息の混ざったような声ではなく、少し硬めの鼻声を意識して「んーんー」と何度か繰り返してみましょう。
2. 舌の動きをよくするトレーニングをおこなう
舌の動きが悪い人は、毎日舌をよく動かし、舌の筋肉を鍛える方法が有効です。
特にカ行・タ行・ナ行・ラ行の計20文字は舌をよく使うので、「カキクケコ・タチツテト……」と一行ずつ発声する練習をおこないましょう。慣れてきたら、「カト・ラチ……」など、4行の言葉をランダムに組み合わせて練習すると、舌が滑らかに動くようになります。
早口言葉を繰り返したり、舌を回す・舌を突き出すといった舌トレーニングを続けたりする方法も効果的です。
3. 腹式呼吸を意識する
歌の練習でよくいわれる「お腹から声を出す」を実行するためには、呼気(吐く息)量を増やせる腹式呼吸をマスターする必要があります。
息を吸うときにお腹をふくらませ、吐くときに凹ませることを意識すると、胸で呼吸する胸式呼吸よりも多くの空気を取り込めるようになり、ハキハキとした発声になります。
腹式呼吸は、前傾姿勢をとることで簡単におこなうことが可能です。そして、息を吸うことよりも吐く意識を強く持って声を出してみましょう。
4. 喉の筋トレをおこなう
喉の筋肉が弱い場合は、喉の筋トレをおこなう習慣をつけましょう。ここでは、声帯を閉じる力を増やすトレーニングをご紹介します。
やり方は以下のとおりです。
- 喉の奥の方で「あー」と硬い声を出してみる
- なるべく息を混ぜないように気をつけながらスタッカートで「あ・あ・あ」と短い音で発声する
このトレーニングをおこなうと、負荷をかけなくとも力強い声が出せるようになります。ただし、効果が絶大な分、トレーニング中は無理をしすぎると喉が疲労しやすいため、短時間に留めておきましょう。
5. ゆっくりと抑揚をつけて話す
声がこもっている人の言葉は聞き取りづらいので、なるべくゆっくり、抑揚をつけて話すよう心がけましょう。重要なポイントを強調するなど、メリハリをつけて話すことで、相手に伝わりやすくなります。
また、一語一語に意識を集中して話すようにすると、発声や滑舌も改善されやすくなるので一石二鳥ですよ。
声のこもりは原因を突き止めて対処すれば改善できる!
声がこもる人は、何度も聞き返されたり、誤った内容が伝わってしまったりするなど、日常生活で苦労を強いられがちです。もしかしたら、やる気がないように見られてしまった経験もあるかもしれませんね。
声がこもるのは、喉の筋肉の衰えや滑舌の悪さ、姿勢の悪さなどが原因です。私生活だけでなく、場合によっては仕事にも影響を及ぼす可能性がありますので、声がこもる原因をしっかりと突き止め、適切なトレーニングで改善を目指しましょう。
「声がこもる原因がわからない」「トレーニングしたけどなかなか改善されない」という方は、ボイトレスクールに通ってプロの指導とアドバイスを受けるのがおすすめです。
Beeボイストレーニングスクールでは、「話し方」を基礎から学べるレッスンを実施しています。一人ひとりの声の悩みや要望に合ったメニューやカリキュラムを提案いたしますので、こもり声に悩んでいる方はぜひお気軽にご相談ください。
Beeボイストレーニングスクールで無料体験レッスンを受けるならコチラ


![Beeボイストレーニングスクール[Bee voice school]](/voice/assets/img/parts/h-site-logo-voice.png)
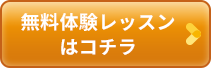
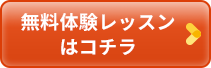
![[フリーダイヤル]0120-015-349(イコーミュージック)携帯電話からも通話可能](/voice/assets/img/parts/h-contact-tel.png)